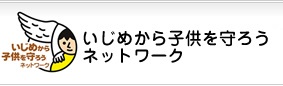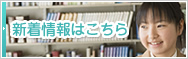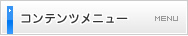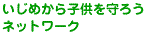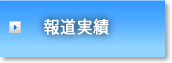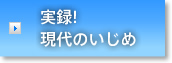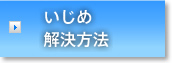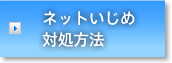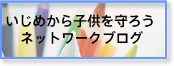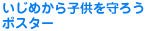2025年8月の代表メッセージ
8月の代表メッセージ
☆2025年8月16日☆
[いじめから子供を守ろう メールマガジン]
◇ 代表メッセージ ◇
■□ 文科省「経年変化分析調査」結果公表 学力低下が顕著 □■
暑い夏という言葉では物足りなく感じる猛暑に続いて、
豪雨が日本を襲うなど、天気が安定しませんね。
高校野球も今年は暑さ対策で、2部制が採用されました。
その高校野球では、出場校のいじめ問題が大きく世間を騒がせています。
いじめ問題で大切なことは、「誰が被害者」で、「誰が加害者」なのかを明確にすることです。
加害者のいないいじめは、絶対に起きません。
このことを常に忘れてはなりませんと、私たちは訴えています。
そして、加害者には、明確な措置をすることです。
大人の事情を「いじめ問題」に絡ませないことが重要です。
子どもたちを守ることが最優先されるべきなんだということを理解し、
いじめ解決を図ることが、とても重要です。
さて、7月には、子どもたちの学力について、ショッキングな報道が続きました。
まずは、7月14日、文科省から、「全国学力・学習状況調査」(全国学力テスト)の結果が公表されました。
続いて、7月31日には、全国学力・学習状況調査の一つとして、
2024年5月~6月に実施した「経年変化分析調査」の結果が公表されました。
この両者共に、顕著な学力の低下が報告されました。
全国学力テストの結果について、読売新聞の記事を引用いたします。
——
文部科学省は14日、小学6年と中学3年を対象に今年4月に実施した
全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の平均正答率などを公表した。
中学国語で記述式の平均正答率は3割に届かず、3割近くが無解答だった問題もあった。
中学国語は全14問で平均正答率は54・6%だった。
問題形式別にみると、選択式(8問)64・2%、
短い言葉や正しい漢字を答える短答式(2問)73・8%に対し、
記述式(4問)は25・6%にとどまった。
記述式の中でも、物語の構成や展開について、
自分の考えとそう考えた理由を書く問題は平均正答率が最も低い17・4%だった。
また、この問題は27・7%が無解答だった。
——
記述式は全国の生徒の1/4しか答えられなかったなど、信じられない結果です。
なお、従来は分析結果などを7月下旬に公表してきたが、
今年度は3回に分けて公表されるとのことです。
また、文部科学省および国立教育政策研究所は、
7月31日に2024年5~6月に実施した調査結果を
「令和6年度全国学力・学習状況調査 経年変化分析調査・保護者に対する調査の結果(概要)」
として公表しています。
(https://www.nier.go.jp/24chousakekkahoukoku/kannren_chousa/pdf/24keinen_summary.pdf)
全国学力テストとは別の調査であり、
抽出された国・公・私立の小学校6年生、中学校3年生の児童生徒を対象に、
3年ごとに、調査されたものです。
前回は、2021年でした。
文科省は、「国全体のスコアの推移(基準年・2016年との比較)」として、以下のように述べています。
1.小学校国語・算数、中学校国語・英語については、本調査のスコアの低下が見られた。
2.中学校数学については、本調査のスコアの変化は見られなかった。
としています。
加えて、
「児童生徒の学校外での過ごし方」として、
1.学校外での勉強時間は前回調査から減少。
学校外での勉強時間が長いほど、経年変化分析調査のスコアが高い傾向。
2.テレビゲームの使用時間は前回調査から増加。
テレビゲームの使用時間が長いほど、経年変化分析調査のスコアが低い傾向。
3.スマートフォンの使用時間も前回調査から増加。
スマートフォンの使用時間が一定程度を超えると、経年変化分析調査のスコアは低下。
という分析をしています。
「子供の学校外での過ごし方に影響を与えている可能性があるもの」として、
1.子供と勉強の話をする保護者の割合は減少(そのような保護者の子供の方が勉強時間が長い。)。
2.学校生活が楽しければ、良い成績を取ることにはこだわらない保護者の割合は増加
(そのような保護者の子供の方が勉強時間が短い。)。
3.「ゲームの時間を限定している」保護者の子供の方が、テレビゲームの時間が短い。
4.「スマホルールを守るよう促す」保護者の子供の方が、SNSや動画視聴の時間が短い。
5.保護者のテレビゲーム、SNS・動画視聴の使用時間がそれぞれ長いと、子供の使用時間も長い。
さらに、
6.授業が「よく分かる」と回答している児童生徒の方が勉強時間が長く、
テレビゲーム、SNS・動画等の時間が短い。
ただし、授業がよく分かる場合も分からない場合も、
家で保護者と勉強の話をする児童生徒の勉強時間が長い。
という報告がなされています。
朝日新聞には、
——
成績が下がった要因について文科省は「明確には示せない」とする。
ただ、中学英語はコロナ禍が影響した可能性を挙げた。
中3生は小学校で外国語を習い始めた時期がコロナ禍と重なる。
「小学校はコミュニケーション重視の指導だが『話すこと』が積極的にできなかった影響」とみる。
ある文科省幹部は「こんなに有意に下がったことはない。深刻だ」と明かす。
学力に関する文科省の専門家会議に長く関わる耳塚寛明・お茶の水女子大名誉教授(教育社会学)は
「驚いた。要因は複合的で、一つずつ確認する作業が必要」と指摘した。
—–
と学力低下の原因の一つにコロナ禍での影響を挙げています。
結局、文科省の方針によって、学力が低下したと言えるのではないでしょうか。
オンライン授業やGIGAスクールによる弊害が出ているようにしか見えません。
ある意味、原因・結果の連鎖でしかなく、当然の結果と言えます。
さらに残念なことに「成績は気にしない」という保護者が多くなりつつあることも気になります。
しかも、その保護者の姿勢の影響が結果に表れているというのですから、
「教育立国」としては、国の未来にも関わりますし、
なによりも子どもたち自身の未来にも影を落とすのではないでしょうか。
子どもたちの夏休みもまもなく終わりますが、
学力低下の観点からも、宿題も見てあげることも必要だと思います。
また、例年、9月1日は、子どもたちの自殺が一番多くなると言われております。
夏休みを満喫した子も、
暑さや天候の影響で、せっかくの計画が変わってしまった子もいるでしょうが、
すべての子どもたちに、元気よく登校し、学校生活に臨んでてもらいたいものです。
何か気になることがありましたら、早めに学校などに相談してみてください。
こちらにも、ご遠慮なくご連絡いただきましたら幸いです。
一般財団法人 いじめから子供を守ろうネットワーク
代表 井澤一明